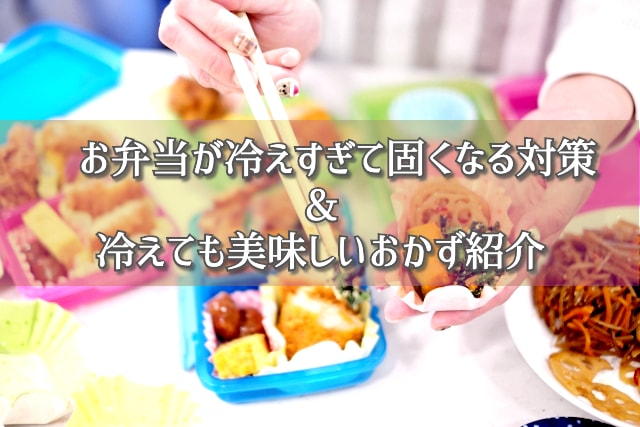
毎日のお弁当作り、お疲れ様です( ^-^)o旦
梅雨時期や夏場のお弁当、いつも以上にとっても気を使いますよね。
食中毒にならないようにせっせと保冷剤を入れていたら、
逆に冷えすぎてキンキンなお弁当で美味しくないと言われたことありませんか?
わたしはあります^^;w
今回は、実体験を交えながらお弁当が冷えすぎないコツを紹介します。
夏のお弁当が冷えすぎてかたくなってしまう理由
梅雨や夏のお弁当には、腐らないように保冷剤を入れている人も多いかと思います。
保冷剤を入れる理由はもちろん「食中毒対策」ですよね。
保冷剤が必要な期間や温度については、こちらの記事で詳しく書いていますが、さらっとおさらいしておくと、
食中毒を引き起こす細菌は20度くらいから活発になり、30度から40度になると菌の増えるスピードが高まると言われています。
そこで、この温度にならないように活用しているのが保冷剤ですよね。
でも、お弁当を食べるときに冷えすぎて固くなっているということは・・・?
保冷剤で冷やしすぎているということになりますよね。保冷剤の量の目安って難しい・・
1番わかりやすい目安としては、お弁当を食べるときに「保冷剤が溶けていない」とか「お弁当がキンキンになる」などの状態であれば、そこまで冷やさなくてもいい環境で保管できているということになると思います。
食中毒の元となる細菌にとっていい環境なのはなまぬるい状態。
その状態を作らないための保冷剤なので、冷房などが効いているところでの保管であれば、お弁当が傷む環境ではない場合もあります。
そこで、冷えすぎるお弁当にならないための対策方法を紹介していきますので参考にしてくださいね!
お弁当が冷えすぎる時の対策方法

ここでは、保冷剤を使う場合と使わない場合での対策を紹介していきます。
通学・通勤やお弁当を食べるまでの保管条件によって試行錯誤が必要かと思いますが、
今回紹介する方法は
・保冷剤の入れ方を変える
・お弁当箱の素材を変える
・保冷剤なしでの対策
となっていて、どれも簡単にできることかなと思います。
ぜひ色々試してみて、ちょうどいいお弁当の傷み対策を見つけてくださいね。
保冷剤のサイズを変える
まずは、保冷剤を小さいものに変える方法から。
お弁当が冷たいということは、保冷効果が強すぎると考えられますよね。
保管環境に合わないほど、大きくて保冷時間の長い保冷剤を使っていると冷えすぎてしまいます。
保冷剤には種類があるので全部ではありませんが、小さい保冷剤を保冷バッグに入れた状態で大体1時間半で溶けると言われています。
大きい保冷剤を使っている場合は、小さい保冷剤に変えて数を調節してみましょう。
また、大きい保冷剤を使う場合でも、少し溶かしてから保冷バッグに入れると保冷時間が短くなるので冷えすぎ対策になります。
小さいお子さんだと難しいかもしれませんが、お弁当を食べる1時間前などに保冷剤を出しておくことでも、食べるときの冷たさがマシになりますよ。
保冷剤の入れ方を変える
保冷剤を使うときは保冷時間を守るためやカバンの中が濡れないように、保冷バッグを使っている方も多いかと思います。
実は保冷バッグへの入れ方でも、冷えすぎ防止対策ができるんです。
保冷バッグを使う場合には、お弁当を直接冷やさなくても保冷バッグ内の温度が冷えていればいいですよね。
なので、保冷剤が直接お弁当に当たらないように工夫することでも冷えすぎ防止になるんです。
オススメの3つの方法は以下の通りです。
✔︎保冷剤をハンドタオルなどで包む
保冷剤をハンドタオルなどで包んでおくと、直接お弁当箱にあたらないので冷えすぎ防止になります。
また、保冷剤が溶ける時の水分も吸収してくれるので一石二鳥ですね。
ハンドタオルの厚みを変えることで、冷え具合をある程度、調節できると思います。
✔︎保冷バッグの中で保冷剤が動くようにする
保冷バッグの中に入れた保冷剤を動くようにしておくと、一ヶ所のみが冷えるのを防げます。
これは、お弁当箱・保冷剤・保冷バッグの大きさによって、どのくらい動くかが変わってきます。
保冷バッグを少し大きめにして、保冷剤が保冷バッグ内で動くようにするといいでしょう。
また、ご飯やお肉類は冷えると固くなって美味しくなくなります。
これらの食材からはできるだけ離して保冷剤を入れることを心がけてみてくださいね。
✔︎保冷剤を入れるポケットがついている保冷バッグにする
最近ではポケット付きの保冷バッグも売っています。
ポケットに入れておくことで、お弁当の上に直接置くよりも保冷剤が触れるところが少なくなります。
こちらの保冷バッグは、バッグとポーチの2個がセットになっていて、どちらにも保冷剤をいれるメッシュポケットつき。
|
|
バッグだけ、ポーチだけでも使えて内ポケットつきってかなりありがたい構造ですよね。
値段も手頃で、この夏売り切れ必至っぽいです(・ω・)
お弁当箱の素材を変える
お弁当箱そのものの素材によっても、保冷剤からの冷たさの伝わり方に違いがあります。
もし使っているお弁当箱がアルミなどの熱伝導の良いものであれば、冷えやすくキンキンになってしまう可能性が高いです。
その場合には、プラスチックなどの素材に変えてみてください。
また、サーモスなどの暖かいまま持っていけるお弁当箱もありますが、こちらは徐々に温度が下がっていくことを考えるとちょっと不安が残りますね。。
もし菌がほとんど繁殖しないと言われている60度以上を維持し続けることができれば安心ですが、食べるまで維持できるかどうか?によると思います。
もちろんお弁当はホカホカの状態が一番美味しいですが、ホカホカのお弁当が冷めていく途中で出す蒸気(水分)を考えても、夏場の暖かいお弁当はちょっと危険かな、と思います。
ただ、真空で保温機能が高いものに関してはお弁当の中の温度変化が少ないので、
熱湯でお弁当箱を温めておいて「あつ〜い状態で入れる」「6時間以内に食べる」など条件によっては大丈夫なようですよ。
温度変化の少ないお弁当箱なら、逆にそうめんのような冷たい麺類などにはとても良さそうですね!
保冷剤の代わりになるアレを使う
保冷剤で冷えすぎる場合には、他のものを代用するという手もあります。
保冷剤の代わりになるもので言えば、以下の2つが手軽にできる方法かなと思います。
✔︎ペットボトルを凍らせる
お茶を入れたペットボトルを凍らせて保冷剤代わりにする方法です。
この場合の時のポイントは、お茶の量を調節して凍らせること。
お茶をペットボトルに半分だけ入れて凍らせて、朝に残りの半分のお茶を足すなどで凍らせる量の調節ができるので冷えすぎ防止にすることが可能です。
お弁当を食べる時の冷え具合で凍らせるお茶の量を変えるという、簡単だけどとてもいい方法だと思います^^
✔︎凍らせたゼリー
ゼリーも保冷剤代わりによく使われる方法です。
数を調節して冷やし具合を変えることができますし、美味しくてオススメです。
食後のデザートにもなるので、甘いものが好きなお子さんなどにはぴったりの保冷剤となりますね。
保冷剤なしでの対策方法
もし、クーラーがあるなどの場合で保冷剤なしでも行けそうだけど、夏は食中毒が怖いなと思う場合は、
保冷剤なしでのお弁当対策をしましょう。
お弁当を傷まないようにするには、
・蓋の裏にわさびを塗る
・生野菜は入れない
・できるだけ水分を切る
・傷みやすい食材は避ける
などの方法があります。
また、ご飯には梅干しを混ぜ込むことで、抗菌効果が期待できます。
ポイントとして、梅干しは丸々1つをポンと入れるだけでは、梅干しがついているところ周辺以外の抗菌効果は薄くなってしまうので、
炊飯器に梅干しを入れて一緒に炊き込むか、炊けたご飯に混ぜ込むのがオススメです。
また、裏技的にお茶づけの素を混ぜ込むという方法もあります。
塩分とお茶の抗菌作用がありますし、梅干し茶漬けならより期待できる気がします^^
夏場には具入りの炊き込みご飯や混ぜ込みご飯ができないので、味を調節しつつ、お茶づけの素を使って美味しいご飯にしてもいいですね。
冷えても美味しいおかず
最後に、保冷剤を入れて冷えてしまっても美味しく食べられるおかずをいくつか紹介します♪
温かい状態だとお弁当に入れるのが怖いおかずでも、お弁当が冷えてしまうなら逆に冷えても美味しいおかずを入れてしまおう!という逆転の発想ですw
・ナポリタン
・焼きそば
・ポテトサラダ、かぼちゃサラダ、ミモザサラダ
・中華春雨
・ささみのごまマヨネーズ和え
・ゆでタマゴ
など
・ツナマヨ
・たらこ
など
(コンビニのおにぎりを参考にするといいかもです)
保冷剤で冷えてしまうお弁当では、常温だと不安なマヨネーズを使ったおかずもイケると思います。
コツはできるだけ水分なくすことと、冷めると味が薄く感じるので気持ち濃いめに味付けするといいと思います。
また、牛肉は冷えると固くなるので冷たいお弁当には不向き。
バターなどの脂分も冷えると固まるので使わない方が美味しいお弁当になると思います。
どうしても保冷剤で冷やしておかないと不安になる夏のお弁当には、冷えても美味しいおかずがオススメです^^
お弁当が保冷剤で冷えすぎて固くなる対策&冷えても美味しいおかず紹介まとめ
お弁当は手間がかかる上に、食中毒対策もしなきゃで本当に大変ですよね^^;
少しでも安心してお弁当を持っていけるように、今回紹介した方法を参考に色々試してくださいね。
また、冷えても美味しいおかずのレパートリーが増えれば、梅雨や夏のお弁当の具に困らなくなります。
参考になれば幸いです^^


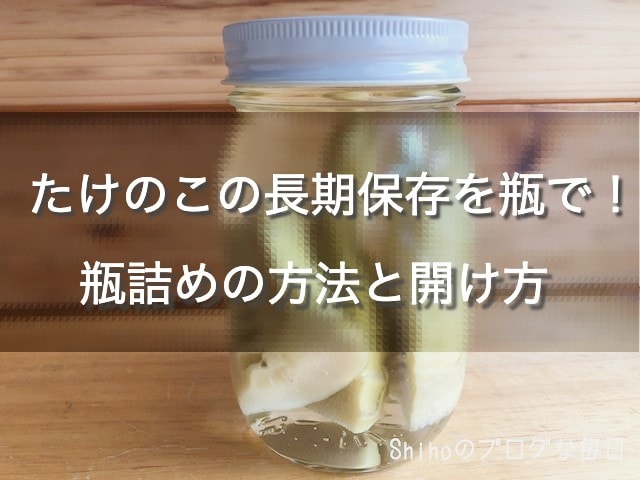
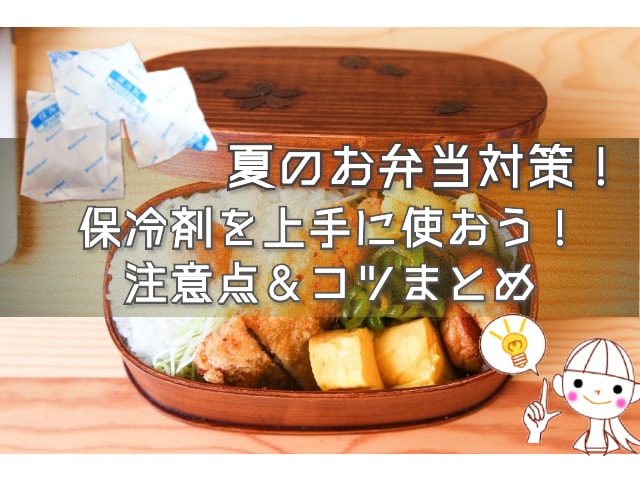
コメント